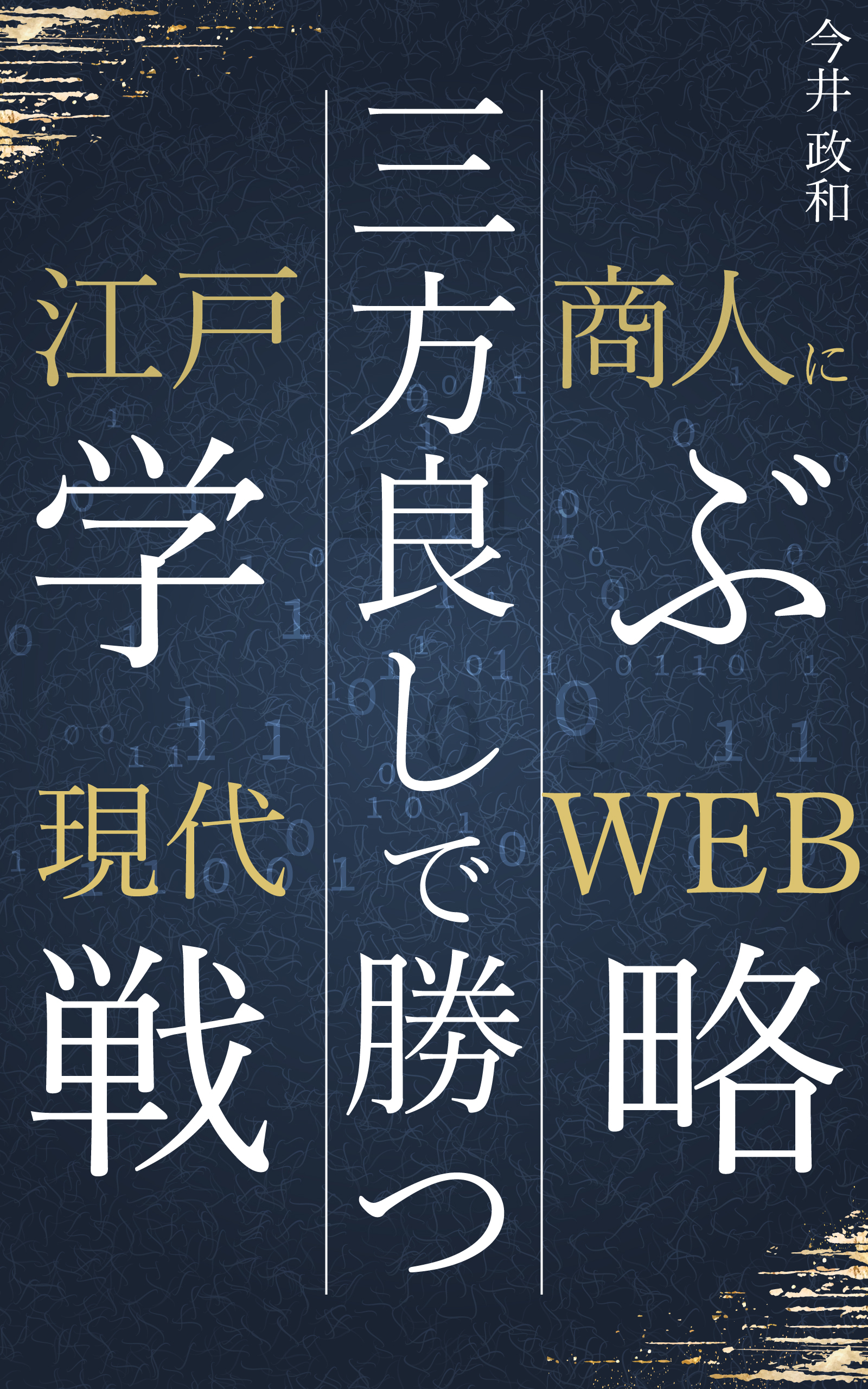はじめに|「なんとなく」から抜け出すために
UIデザインを始めたばかりの頃、よくある悩みが「何から手をつけていいか分からない」というもの。色を選んでみたり、フォントを変えてみたり、ボタンをそれっぽく置いてみたり……でも、どこか「芯がない」と感じていませんか?
この記事では、実践的かつ再現性のあるUIデザインの進め方として、
構造 → 視覚 → 文字
という流れをベースに、初心者からでも迷わず進められる3ステップ設計法を紹介します。
1. 構造を決める|まずは“骨組み”から
UIデザインの土台は、「どの情報をどこに配置するか」を決めるワイヤーフレーム設計です。構造設計が甘いと、どんなに見た目が美しくてもユーザーは迷ってしまいます。
✅ 構造で考えるべきこと
- 目的:ユーザーに何をしてもらいたいか
- 優先順位:どの情報を目立たせるか
- レイアウト:視線の流れ、階層、余白
ワイヤーフレームは「白黒・線だけ」で十分。“見た目を考える前に、機能と意図を決める”のが成功のカギです。
2. 視覚を整える|カラーとイメージで雰囲気を与える
構造が固まったら、次に取りかかるのが「視覚のデザイン」。ここで初めてカラー・画像・装飾の出番です。
✅ 視覚の役割とは?
- 視認性:目に入りやすく、読みやすくする
- 印象操作:信頼感・活発さ・安心感などを演出
- 情報の区分け:色で意味の違いを示す
たとえば、CTA(Call To Action)ボタンは「ユーザーの注意を集める色」を使うのが定石。背景や画像選びも、情報設計の“裏付け”があってこそ意味があります。
3. 文字を整える|最後に伝える力を高める
構造と視覚が整ったら、最後に取り組むのがタイポグラフィ(文字の設計)です。
✅ タイポグラフィが重要な理由
- 情報の階層が明確になる(見出しと本文の差)
- ユーザーの読解速度が上がる
- サイト全体の品格やトーンが統一される
特に日本語Webでは「読みやすさ」がデザインの信頼性に直結します。フォント選び・サイズ・行間・文字間などは、見た目以上に“意味”を持っています。
UIデザインの設計順を守ると、迷いが減る
順番を意識せずにデザインを始めると、どこかで必ず手が止まります。その理由は「判断軸がないから」。
①構造 → ②視覚 → ③文字
この3ステップを守れば、
- “なんとなく”で選んだ配色が減る
- フォント選びに迷わなくなる
- 修正やレビューの基準が明確になる
など、すべての判断に「理由」が持てるようになります。
まとめ|順番が、UIの質を決める
UIは“感覚で組み立てるもの”ではなく、“構造化された判断”の積み重ねで作られるものです。
色やフォントに手を出す前に、まずは骨組みをしっかりと。構造 → 視覚 → 文字の順に進めることで、見た目だけでない“本質的に伝わるUI”が実現します。