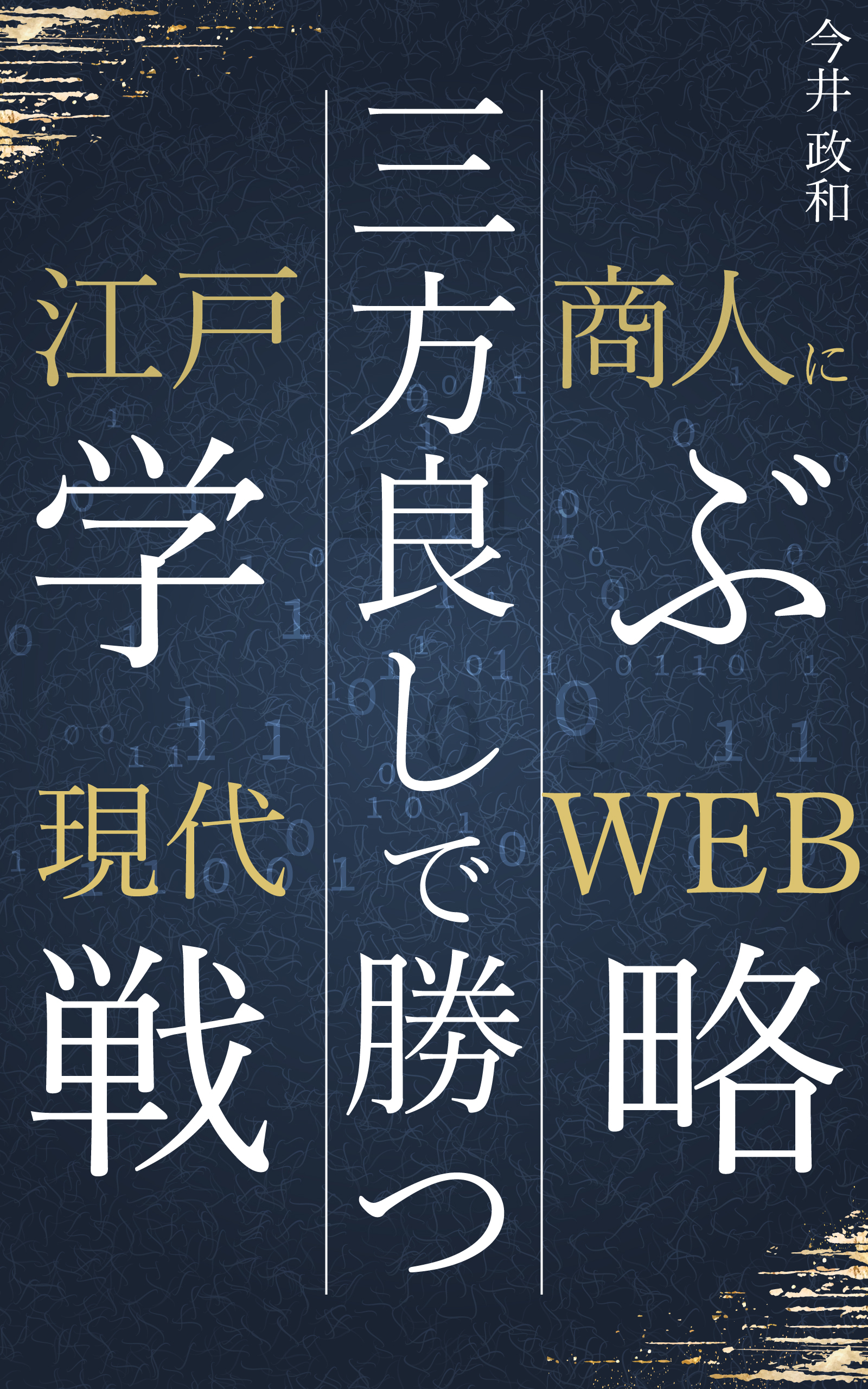はじめに
Web制作とSREをどう並行させる?学習ロードマップと実務での活かし方
Web制作をしていると「もっと安定的にサイトを運用したい」「クラウドやインフラにも強くなりたい」と思う瞬間があるはずです。
そんな時に出てくるキーワードが SRE(Site Reliability Engineering)。一見するとWeb制作とは遠い領域に感じますが、実は両者は強く結びついています。
本記事では「Web制作を軸にしながらSREを並行して学ぶにはどうすれば良いか」をロードマップ形式で解説します。
Web制作の強みをSREに活かす
Web制作の経験はSREを学ぶ上で大きな武器になります。
- パフォーマンス最適化
Core Web Vitalsの改善や画像最適化は、そのままSREの「SLO(Service Level Objective)」改善に直結します。 - WordPress運用経験
サーバーリソースの制約やキャッシュの仕組みを意識することは、インフラ設計に応用できます。 - UI/UXへの感度
SREでもユーザー体験を重視する視点(SLI: Service Level Indicator)が求められます。
つまり、Web制作をしている人は すでにSRE的な視点を一部持っている のです。
SREを学ぶメリット
では逆に、SREを学ぶとWeb制作にどう役立つのでしょうか?
- クラウド知識の習得
AWSやGCPを理解することで、自作サイトをスケーラブルに展開可能。
→ 参考: roadmap.sh DevOpsロードマップ では、学ぶべきクラウドの領域が体系的に整理されています。 - 自動化の導入
CI/CDパイプラインを構築できれば、デプロイ作業がボタン一つで完了します。 - 運用・監視スキル
Uptime監視やログ解析に強くなることで、納品後の保守・運用サービスを提供できるようになります。
→ UptimeRobot のような無料監視サービスを導入すれば、個人制作サイトでもすぐに実践可能です。
並行学習の進め方
学習フェーズを分ける
Web制作に直結する領域から
- CloudflareやCDN導入
- サーバーレスポンス最適化
- 簡易モニタリング(UptimeRobot, New Relic Lite)
Redditでも「SREにはフルスタックの理解が必要だが、まずは自分のサイト監視から始めるのが良い」との声があり、学習を小さく始める意義が強調されています。
基盤力を強化する領域
- Linuxコマンド基礎
- Docker / コンテナの基礎
- IaC(TerraformやAnsible)
→ Google公式SRE本 では、こうした基盤技術を背景に「信頼性エンジニアリング」を体系立てて解説しています。
学習の時間配分
- 案件やWeb制作スキル強化(収益直結)
- SREの基礎学習(AWSハンズオンやDocker環境構築)
- WordPressをDockerで動かし、UptimeRobotで監視する小さなプロジェクトを作る
実務での掛け合わせ例
- 小規模案件
LP制作+AWSデプロイまで対応し、「運用に強い制作者」として差別化。 - チーム開発
フロントエンド担当でありながら、CI/CDパイプラインを設定できることでチームから重宝される。 - フリーランス案件
「納品+保守・運用サービス」をパッケージ化して、継続収益につなげる。
実際、海外のエンジニアコミュニティでは「Web系の基礎+SREの運用知識を持つ人材は、DevOpsやSREに移行しやすい」とよく言われています。
キャリアパスの描き方
Web制作とSREを並行すると、キャリアの選択肢は広がります。
- フロントエンドエンジニア → DevOps → SRE
- Web制作フリーランス → 運用・保守を含むディレクション
- SREを本業に → 副業としてWeb制作案件を続ける
両立を目指すなら、まずは 「Web制作7割、SRE3割」 の比率から始めるのがおすすめです。
まとめ
- Web制作とSREは対立するのではなく、補完し合う関係
- 並行学習のコツは「直結する部分から手を付ける」こと
- 小さなプロジェクトで実践しながら、自分の強みを拡張していく
Web制作を基盤に持ちながらSREを学ぶことで、単なる「制作者」から「運用まで支援できるエンジニア」へと進化できます。
→ まずは自分のサイトをクラウド上に置き、監視を導入するところからスタートしましょう。