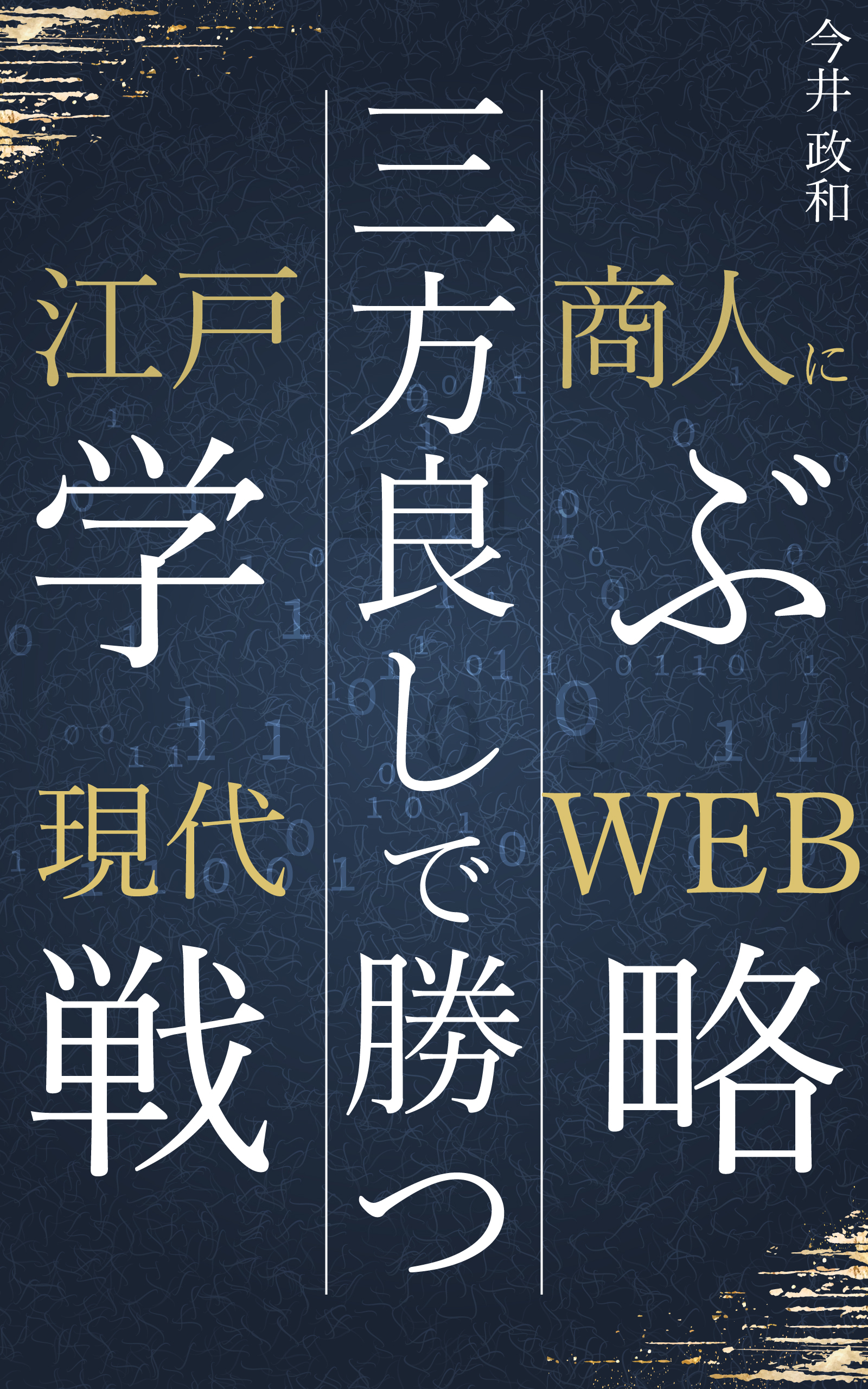導入
ここ数年で「WEBマーケター」という肩書きを名乗る人が一気に増えました。SNS広告を運用したり、InstagramやTikTokの投稿を分析・改善したり、SEOでアクセスを伸ばしたり…。確かにそれらは重要な仕事です。しかし同時に、こうした仕事ばかりをマーケティングと呼ぶことに強い違和感を覚える人もいるのではないでしょうか。
実際に私は、広告やSNSよりも、直接的な営業や販路の見直しが大きな成果につながるケースを多く経験してきました。だからこそ「マーケター=SNS運用屋」というイメージは本質を外している、とはっきり言えます。
マーケティングの本当の役割は、単なる運用や広告ではありません。経営や営業と密接につながりながら、市場における「売れる仕組み」を設計することです。本記事では、マーケティングが誤解されてきた背景を整理しつつ、営業・経営の視点から「本当のマーケティングとは何か」を考えていきます。
第一章:なぜ「マーケター=SNS運用屋」という誤解が生まれるのか?
SNS代行の需要拡大
企業にとってSNSは欠かせない集客チャネルになりました。InstagramやTikTokでの発信、X(旧Twitter)での認知獲得は、多くの企業にとって生命線となっています。こうした背景から「SNSを運用できる人材」が一気に求められるようになり、結果として「マーケター=SNS運用ができる人」というイメージが浸透してしまいました。
数字で成果を示しやすいから
SNSのフォロワー数、いいね数、リーチ数、広告のクリック率…。これらは成果を「見える化」しやすいため、評価されやすい特徴があります。しかし実際には、フォロワーが増えても売上につながらないケースも多く、事業全体を見渡したときに意味を持たないことも少なくありません。
運用がマーケティングのすべてではない
広告運用やSNS施策は確かにマーケティングの一部ですが、「それだけ」で完結してしまうと販促活動の域を出ません。つまり「広報」や「集客」を担う存在になりがちで、本来のマーケティングの役割からは外れてしまうのです。
第二章:営業から見たマーケティング
営業の現場を知らない戦略は机上の空論
マーケティングを考える上で、営業経験は不可欠です。なぜなら営業こそが顧客と直接向き合い、購買心理や行動をリアルに感じ取る場だからです。
- 個人営業では、顧客の生活背景や感情に触れ、購買動機のリアルを知ることができます。
- 法人営業では、組織としての意思決定プロセスを理解することが求められます。
これらを知らないまま市場戦略を設計しても、現場では響かない施策になってしまう。営業を経験することで初めて「なぜこの販路が効くのか」「どう伝えれば顧客に届くのか」を肌で理解できるのです。
営業→市場営業(マーケティング)へのステップ
私は「個人営業」「法人営業」ができて初めて「市場営業(マーケティング)」を語れると考えています。顧客一人ひとりに売るスキルを積み上げ、それを市場全体に拡張していくのがマーケティングの役割だからです。
第三章:経営とマーケティングの関係
経営は「商品力」をつくる
経営者の仕事は、事業の源泉となる商品力を磨くことです。新しい価値を市場に生み出し、それを持続的に提供できる体制を整えることが経営の役割です。
マーケティングは「販路の最適化」をする
一方で、いくら優れた商品でも販路が適切でなければ売れません。マーケティングはその商品の価値を市場にどう届けるか、販路やチャネルを最適化する仕事です。
営業は「売上に直結させる」
そして営業は、顧客と接点を持ち、実際に売上に変換する役割を担います。
経営・マーケティング・営業はこのように三位一体で事業を動かすのです。
第四章:本当のマーケティングとは
「売る」ではなく「売れる仕組みを作る」
マーケティングの本質は、営業の代わりをすることではありません。営業が楽になる仕組みを作り、商品が自然に売れていく状態を整えることです。
顧客理解と市場設計
- 誰が何を求めているのかを徹底的に理解する
- そのニーズを満たす場(市場)を設計する
- 最短距離で商品と顧客を結びつける導線を整える
この過程で広告やSNSが必要になることはありますが、それはあくまで「手段」であり「本質」ではありません。
第五章:SNS運用の限界と役割
SNSは重要だが万能ではない
SNSは認知拡大や顧客接点の増加に有効ですが、それだけで売上が立つわけではありません。フォロワー数や再生回数に振り回されると、本質を見失います。
SNSをマーケティングに組み込む視点
- SNSは販路の一部
- 商品力・営業戦略・販路設計と噛み合って初めて成果を出す
- 「SNS運用屋」から「事業全体を見渡せるマーケター」への視座が必要
販路を変えたら売上が伸びたケース
私がこれまでに見てきた中で「販路を変えるだけで売上が大きく伸びた」事例は少なくありません。
例えば、あるサービスでは当初「SNS広告を中心に集客」していました。しかしターゲット顧客はSNSよりも検索エンジン経由で情報を集める層が多かったため、広告費の割に成約率が低かったのです。そこで方針を切り替え、SEOとオウンドメディアに力を入れたところ、同じ広告費をかけずとも自然流入からの問い合わせが増え、売上が安定的に伸びていきました。
また別のケースでは、法人営業をSNS経由のアプローチに依存していましたが、ターゲット企業の購買決定プロセスを調べた結果、展示会や業界紙の掲載の方が圧倒的に効率が良いことが判明しました。販路を「SNSから展示会」へとシフトしただけで、半年後には商談数が数倍に増えたのです。
このように、「どのチャネルで顧客と出会うか」=販路の設計こそがマーケティングの核心です。SNSはあくまで一つの手段であり、顧客が本当にいる場所を見極めることが、成果につながるマーケティングです。
まとめ
「WEBマーケター=SNS運用屋」というイメージはあまりにも狭い捉え方です。マーケティングの本質は、経営と営業をつなぎ、商品を市場に最適に届ける仕組みを設計することにあります。広告やSNSはそのための一部の手段でしかありません。
マーケティングは“運用”ではなく“設計”です。
そしてその設計の質を決めるのは、営業の現場経験や経営の視座に裏打ちされた「販路最適化の力」だと、私は強く思います。