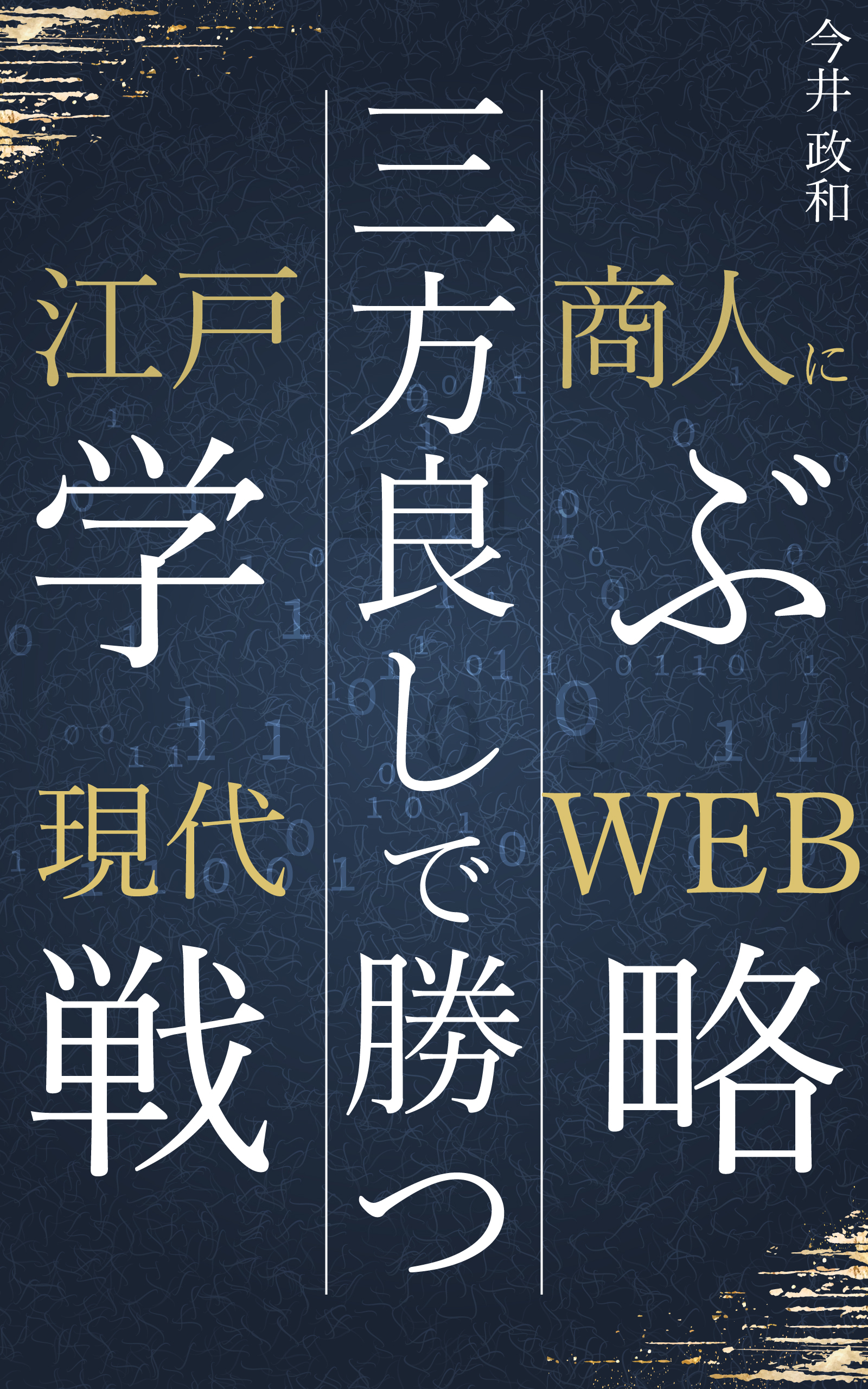Webライターとディレクター負のスパイラル ― なぜ稼げないのか?
AIの普及によって「Webライターはもう稼げないのではないか」という声をよく耳にします。
確かに、調べた情報をまとめただけの記事や、文字数を埋めるだけの文章はGPTに代替されつつあります。
しかし、ライターが稼げない原因はAIに奪われたからではありません。
もっと根本的な問題が日本のWeb業界には存在しています。
それが 「ライターが成長できず、ディレクターも育たないスパイラル」 です。
ライターの課題:文章は書けても構造を理解していない
「文章を書くのが好きだから」という理由でWebライターを始める人は多いでしょう。
しかし、そこで求められるスキルは単なる文章力ではありません。
実際のライター志望者に圧倒的に欠けているのは次のような力です。
- HTMLやマークアップの基本知識
- 検索意図を理解した記事構成力
- 内部リンクを意識したサイト全体の設計視点
こうした「Webの文法」が抜け落ちているため、結果として
単価0.5〜1円で量産記事を書くだけの存在になってしまうのです。
ディレクターの課題:内部SEOと外部SEOを理解できない
さらに問題はディレクター側にもあります。
- 内部SEOと外部SEOを両輪で理解していない
- 「関連記事を自動で貼れば内部SEO」と勘違いしている
- コーダーやエンジニアの経験がなく、構造を評価できない
本来、内部SEOとは「検索意図に沿って記事同士を結びつけ、サイト全体で網羅性を高めること」です。
しかし、多くのディレクターはただ関連記事ウィジェットを置いて満足してしまう。
これではSEO効果どころか、ユーザー体験の改善にもつながりません。
評価基準を持たないディレクターが、ライターの成長を止めているのです。
スパイラルの悪循環
こうして業界には悪循環が広がっています。
- ライターは「記事単体」を書くだけで終わり、成長しない
- ディレクターは「記事数」しか見ず、構造を評価できない
- クライアントは「記事数=SEO」と思い込み、成果が出ない
- できる人材がいても正当に評価されない
このスパイラルが、日本のWeb業界を低単価の消耗戦に縛り付けています。
経験を経ないまま肩書きだけの人材
さらに追い打ちをかけているのは、「経験を経ずに肩書きを名乗る文化」です。
- コーダーやプログラマを経験していないのにディレクターを名乗る
- サイト構成を勉強したことがないのにライターを名乗る
実装経験も構造理解もないまま「ディレクション」や「ライティング」を掲げる人材が増え、
教育もされないまま現場に投入される。
これでは、本当に成果を出せる体制が育つはずがありません。
解決策は「業界全体の底上げ」しかない
このスパイラルを断ち切るには、ライターだけを育てても不十分です。
ディレクターだけを鍛えても意味がありません。
必要なのは 業界全体の底上げ です。
- ライターは「文章屋」から「構造を理解する制作者」へ
- ディレクターは「肩書き」から「評価基準を持つ管理者」へ
- そしてクライアントは「記事数信仰」から「戦略的なSEO」へ
ここまで進化しなければ、日本のWeb業界はいつまでも「安さ競争」から抜け出せません。
AI時代でも残る人材とは
GPTが量産記事をいくらでも作れる時代に、残るのは次のような人材です。
- 内部SEOと外部SEOを正しく理解している人
- 記事単体でなくサイト全体を設計できる人
- 一次情報や体験談を持ち込める人
- 人間だからこそできる評価や判断ができる人
つまり「稼げるライター」「成果を出せるディレクター」とは、
AIでは代替できない 構造理解と評価軸 を持った人材なのです。
結論:日本のWeb業界の矛盾を直視せよ
ライターは成長しない。
ディレクターは評価できない。
そして企業は「記事数が多ければSEOに強くなる」と誤解している。
この三重苦が、Web業界全体を低単価・低品質に縛り付けています。
AIの登場で「文章を量産するだけの人材」が不要になるのは必然でした。
本当に問われているのは、ライターとディレクター双方が 構造を理解し、正しく評価できるかどうか です。
業界のスパイラルを断ち切れるかどうか。
それこそが、日本のWebビジネスのみならずビジネス全体が次のステージへ進めるかどうかの分岐点なのです。
筆者の視点について
私はWeb業界だけでなく、自動車業界や保険代理店業を含めたビジネスの現場を長く経験してきました。
その中で共通して感じるのは、「肩書きだけで役割を担う人材が増えると、業界全体の成長が止まる」という現実です。
Web業界におけるライターとディレクターのスパイラルも、まさに同じ構造です。
他業界の経験があるからこそ、あえて強めに問題提起をしています。
「ただ文章が書ける人」「ただ指示を出す人」ではなく、
構造を理解して動ける人材こそが、どの業界でも最後に残ります。